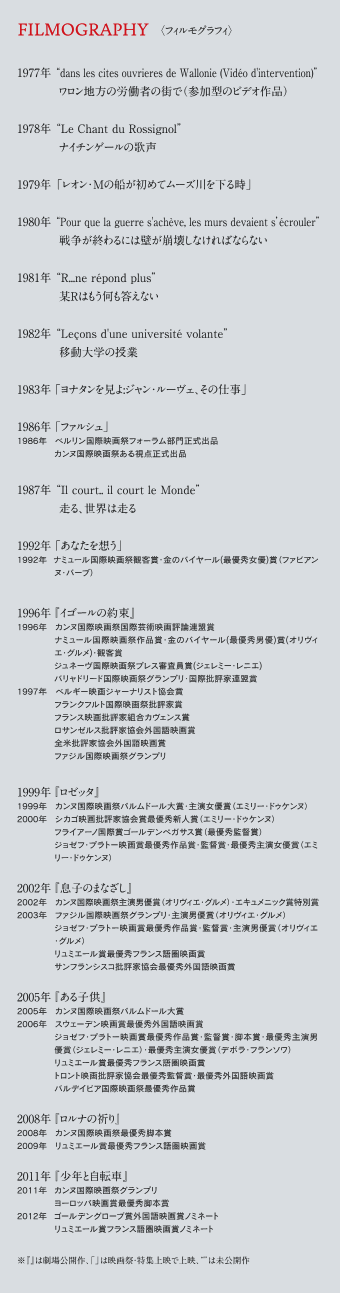兄のジャン=ピエールは1951年4月21日、弟のリュックは1954年3月10日にベルギーのリエージュ近郊で生まれる。リエージュは工業地帯であり、労働闘争のメッカでもあった。ジャン=ピエールは舞台演出家を目指して、ブリュッセルへ移り、そこで演劇界、映画界で活躍していたアルマン・ガッティと出会う。その後、ふたりはガッティの下で暮らすようになり、芸術や政治の面で多大な影響を彼から受け、映画製作を手伝う。原子力発電所で働いて得た資金で機材を買い、労働者階級の団地に住み込み、土地整備や都市計画の問題を描くドキュメンタリー作品を74年から製作しはじめる。同時に75年にはドキュメンタリー製作会社「Derives」を設立する。
78年に初のドキュメンタリー映画“Le Chant du Rossignol”を監督し、その後もレジスタンス活動、ゼネスト、ポーランド移民といった様々な題材のドキュメンタリー映画を撮りつづける。86年、ルネ・カリスキーの戯曲を脚色した初の長編劇映画「ファルシュ」を監督、ベルリン、カンヌなどの映画祭に出品される。92年に第2作「あなたを想う」を撮るが、会社側の圧力による妥協の連続で、ふたりには全く満足できない作品となってしまう。
前作での失敗に懲りた彼らは、第3作『イゴールの約束』では決して妥協することのない環境で作品を製作、カンヌ国際映画祭国際芸術映画評論連盟賞をはじめ、多くの賞を獲得するなど、世界中で絶賛された。続く第4作『ロゼッタ』ではカンヌ国際映画祭で最高賞にあたるパルムドール大賞と主演女優賞を受賞、本国ベルギーでの成功はもとより、フランスでも100館あまりで公開され大きな反響を呼んだ。さらに2002年、第5作『息子のまなざし』でもカンヌ国際映画祭で主演男優賞とエキュメニック賞特別賞をW受賞する。また05年カンヌ国際映画祭にて第6作『ある子供』では史上5組目(他4組はフランシス・F・コッポラ、ビレ・アウグスト、エミール・クストリッツァ、今村昌平)の2度目のパルムドール大賞受賞者となる。第7作『ロルナの祈り』では08年のカンヌ国際映画祭において脚本賞を受賞、そして本作『少年と自転車』は11年の同映画祭グランプリを受賞。史上初の5作連続主要賞受賞の快挙を成し遂げた。
近年では共同プロデューサーとして若手監督のサポートも積極的に行っている。名実共にいまや他の追随を許さない、21世紀を代表する世界の名匠である。
![]()
――『少年と自転車』はどのように生まれたのでしょうか。
リュック(以下L):ずっと頭を離れない物語がありました。ひとりの女性が、暴力の世界に囚われている少年を救いだすというものでした。神経がむき出しになったこの少年が、もう一人の人間によって平和と慰めを得るのです。
ジャン=ピエール(以下J=P):それから、2003年に『息子のまなざし』のために東京へ行った時に、女性の弁護士から児童養護施設に預けられた子どもの話を聞きました。父親は迎えに来ると約束したが、決して来なかった。けれど、ずっと屋根にのぼって父親が来るのを待っていた。しかし、あるとき屋根にのぼることも、親を待つこともやめ、誰のことも信じなくなった、という話でした。すぐには、これをどう映画にしたらいいか分かりませんでしたが、そのイメージが頭の中にずっとこびりついていました。
――サマンサの善意はどこから来ているのでしょうか。
J=P:最初、サマンサを医者にしようかと思っていたのですが、最終的に美容師になりました。彼女はずっとその地区に定住しています。
L:なぜサマンサがシリルに興味を持つのか、観客には分からないようにしました。心理は説明したくなかった。現在を過去で説明してはならない。「彼女はそうするべくしてしている」と観客に思ってもらうようにしたかったのです。
――シリルは常に動いていますね。一カ所にとどまっていない。
J=P:そう。彼はいつも自転車に乗っている。つなぎとめるものが何もない彼は、そうと知らずに、愛を求めているのです。
――あなた方の映画にはしばしば親子関係が描かれます。『イゴールの約束』『息子のまなざし』『ある子供』。なぜですか?
L:私たちはみな「誰かの息子」であり、「誰かの娘」ですからね。
J=P:現在の社会は個人を強調しすぎるように思います。私たちがいつも絆という考えに立ち戻るのは、その反動かもしれません。サマンサとシリルのように、絆が生物的なものとは限りません。
――善意を描くのは難しかったですか。
L:悪のほうがいつだってエキサイティングですから(笑)。もちろん善意の紋切り型に陥るわけにはいきません。相手に対し自分を開き、心を通わせる感情の動きを、できるだけ間近から捉えることが必要だったのです。
J=P:誰かの幸福を願う人物を描くというのは、私たちには珍しいことです。初めて夏に撮影したことで、映画に光と、ある種の優しさが加わりました。それに、セシル・ドゥ・フランスもその明るさを持ち合わせていました。
――有名な俳優を起用するのはあまり例のないことですね。
L:あらかじめ特定の俳優を考えながらシナリオは書きません。シナリオ執筆が終わった時点で、女優を誰にしようか考え、最初に浮かんだのがセシルでした。彼女の身体、顔は“あるべくしてそこにある”となるだろうと思いました。彼女にシナリオを渡すと、すぐに引き受けてくれました。彼女からサマンサの動機についていくつか質問を受けましたが、「サマンサはそこにいる、それだけ」と答えました。彼女は私たちを信頼してくれましたよ。
――シリルを演じたトマ・ドレはどのように選んだのでしょう。
J=P:あの年代のキャストを探すときはいつも新聞に広告を出して募集します。100人くらいの少年たちのオーディションをしました。トマは初日の5番目に来ました。存在感が際立っていましたね。
L:私たちはすぐに、彼のまなざし、強情な、内にこもった感じに打たれたんです。
J=P:彼はセリフを覚える能力にも長けていました。最初のテストは、映画の冒頭の場面でしたが、その時点から、彼がシリルだと感じました。彼は、自分が演じる人物を本能的に理解していました。正確な、人の心を動かすような、しかし、お涙ちょうだい的ではない何かが彼にはあったのです。
L:クランクインする前の1カ月半に及ぶリハーサルの間、トマだけがずっとその場にいました。彼はすでに全ての場面を知りつくしていたから、もう何も要求することはありませんでした。失敗しようものなら、ひどくイラついていました。トマは空手家で、茶帯なんですよ! それで記憶力・集中力があるんですね。
――あなたの映画の常連もいます。オリヴィエ・グルメとジェレミー・レニエ。ジェレミーは、父親という難しい役でした。
L:オリヴィエは三つの役を提示したところ、ビールを出す居酒屋の主人を選びました。ちょっとした場面ですが、彼がいることが、私たちには重要なんです。
J=P:ジェレミーの役はきつい。シナリオを読んで、どんな人物か分かると、「また感じのいい役をみつけてくれたもんだ」と(笑)。しかしまあ、これまでも“感じのいい役”をやってきたわけですからね。
――シナリオの執筆はどのように行われたのでしょう。期間はどのくらい?
J=P:休んでいる時期も含めてトータルで一年。しかし物語はずっと話し合ってきました。
L:人物像と、状況から作業を開始して、面白いと思ったことは全部書き留めます。それから構造を考えだし、第一稿、第二稿、第三稿と、続く。この作業に数カ月かかります。
――撮影は?
L:夜の早い時間も含めて55日間です。でも夜中の1時半を超えることは一度くらいしかありませんでした。何といっても主演は13歳の子供ですからね。事前準備を十分し、撮影が始まってからはそれほどリハーサルはしませんでした。
――『少年と自転車』のロケーションは、街とともに周辺の森もありますね。
L:地理的に、この映画は三角形だと考えていました。街と森と、ガソリンスタンド。森はシリルにとって危険な誘惑の場所です。そこで彼は、不良になることを学びます。街は、父との過去とサマンサとの現在、ガソリンスタンドは、通過の場所で、そこで物語は何度か新しい展開を迎えるのです。
J=P:この映画をおとぎ話のようなものにしたかったのです。悪者たちが少年の幻想を打ち砕いた後、サマンサが妖精のように現れる。この映画を「現代のおとぎ話」という題にしようかとも思っていました。
――初めて劇中に音楽を使いましたね。
L:私たちの映画ではごくまれなことで、ずいぶんためらいました。おとぎ話の中には当然感情の流れがあり、新しい展開を迎える瞬間があります。ある瞬間にかかる音楽は、シリルにとって、心を落ち着かせる愛撫のようなものになるのでは、と思ったのです。