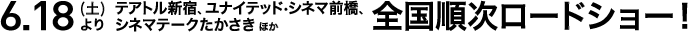自主映画時代から数えて7作目となるオリジナル長編映画である本作『あぜ道のダンディ』で、石井裕也監督は初めて「家族」を直接的に描き切った。
これまでも「家族」の形を取る作品はあっても、「ぶっ壊わして壊れるような『家族』ならなくていい」と監督が以前から発言していたとおり、関係性だけの「家族」に留まっていたように思う。それはそれで監督の現代社会に対する風刺でもあるのだが、それと同時に「家族」に対する照れがあったのかもしれない。
それを今回の企画で「家族」をテーマにあげられた時、監督独特の世界観で「男」を全面に押し出してはいるものの、「それでもお父さんだから、男だから、何があっても守る』という照れのない監督のストレートなまなざしは、これから父親になっていくであろう監督自身を含めた同年代への応援歌であり、こんな時代でも頑張るお父さんたちへ誠心誠意を込めたラブレターなのだろう。
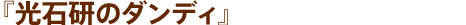
そのラブレターを大声で読み上げてくれた光石研さんは、まさに「平成のダンディズム」を持っている人だった。
光石さんの33年ぶりの主演作ということで、田口トモロヲさんをはじめ、藤原竜也さん、西田尚美さん、岩松了さんという映画界を支える豪華キャストがぞくぞくと勢ぞろいした。これは、光石さんがこれまで築いてきた人望によるもので、プロデューサー陣もこの想定外に驚きを隠せないでいた。
撮影に入ってからも睡眠時間3時間取れれば、万々歳であるタイトなスケジュールにも、弱音を吐くことなく光石さんは笑って泣き怒り、おじさんを真摯に演じていた。その心意気にキャスト・スタッフ全員が光石さんに惚れ、仕事という枠を超え、「光石さんを輝かせるために」動いていた。演技を超えて、光石さん自身の「男気」が映画に焼き付いている。タイトルを『光石研のダンディ』に変えてもいいほどに。

正直言うと、今回の作品は予算的にもスケジュール的にもかなり厳しい現場だった。監督がクランクイン前に「奇跡を5個くらい起こさないと…」と苦笑いしていたのを覚えている。こんなにも厳しい条件の中で準備をするのは無理なんじゃないかという声もスタッフの中には実際あった。けれど、撮影地の「群馬」にはたくさんの高崎ダンディや前橋ダンディたちがいた。
自らの家を撮影地として提供して頂いた山宮家、大半の撮影地を見つけるきっかけとなり、カレーや炭火焼チキンまでご馳走してくれた林さんや相澤さん、仕事返上で協力してくれた居酒屋小塙さんや太陽運輸さん、医療協力までしてくれたひらが脳神経外科の平賀先生など、この世知辛い世の中で、良心だけで撮影協力してくれる人ばかりで、こんな心意気ある人間になりたいと思わせてくれるダンディズム溢れる方々ばかりだった。
撮影を終えて、監督がポロリとこんなことを言っていたのを思い出した。
「現場で誰よりも偉いのは映画。
その映画を作るのは、機材やお金じゃなくて『人間』」
映画だけではなく、すべては、ダメだけど苦悩しながら、小さな希望を見つめ続ける「人間」がこの世界をつくっていくのだということだろう。それが発見できた現場であったこと、それが共有できる人達との出会いそのものが監督の言う「起こさなきゃいけない奇跡」だったように今思う。
『あぜ道のダンディ』アシスタントプロデューサー
中村無何有(なかむら・むかう)
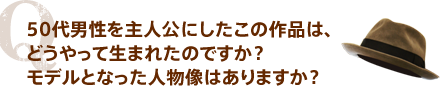
「男」の映画を作ろうと思いました。特に、男の美意識についての映画です。
この時代、誰しもが「男なんて、みんな駄目だ」と気づいてしまったし、正直僕もそう思います。でも駄目だろうが情けなかろうが敗北してボロボロになろうが、男は男を気取って堂々と生きていくしかないのです。その覚悟こそが男の純情、美意識なのではないかと思います。そういう美意識を持っている男を僕は「いい男」と呼んでいます。いや、「駄目だけど、いい男」です。
これからオジサンになっていく身の者として、理想の中年男を描こうとするのはとても自然で当然の流れでした。この映画の主人公、宮田淳一のような男に僕はとても憧れています。
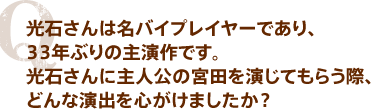
主演のキャスティングはいつもプロデューサーの方にお任せしていますし、それでいいと思っています。実際、完成した映画を観るとこの役は光石研さん以外に考えられなかった、と僕には思えます。 演出する際、「光石研さんを輝かせる」という事を常に第一義的に考えていました。この映画の肝は間違いなくそこですから。具体的な狙いとしては、渋さ、艶やかさ、愛嬌、滑稽さで、そのバランス、配分には特に注意して、かなり細かく言わせて頂いた覚えがあります。

光石さんが主演に決まった時点で、この映画を芝居の映画にしようと考えました。映画ですから芝居をするのは当然なのですが、イメージとしてもっとじっくり芝居だけを見せる映画、という意味です。なので、周りの役には光石さんと本気でぶつかり合っていけるような方々にお願いしたつもりです。演技力云々ではなくて、存在そのもの、人の雰囲気のようなものを見て決めました。
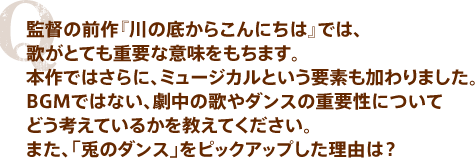
映画の中で歌か踊りは出すべきだと考えています。その方が楽しいですから、という至極単純な理由です。次回作には歌も踊りも出てきませんが、脚本の構造上入れられなかっただけで、基本的には入れた方がいいと思います。 元々日本の童謡が好きで、小さい頃はよくカセットテープで聴いていました。特に滑稽さと、もの哀しくて切ない雰囲気が同居したものが好きでした。主人公が夢の中で子供達のために歌うというシーンに、その雰囲気は最適でした。いろいろな童謡を聴いてみて、『兎のダンス』を選びました。2011年が兎年だったのはたまたまで、完成した後に気づきました。

真田との中学以来の独特の関係性を表現したかったのと、会話にリズムをつけるという狙いです。「宮田」と「真田」という名字は言葉の音韻で選びました。
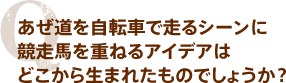
自転車に乗りながら己を競走馬に見立てるのは、 僕が小学校の時にやっていた一人遊びです。

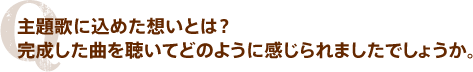
清 竜人さんを信じて、全てお任せしました。最初にお会いした時に、この映画がどこを向いていて、「希望」というものをどのように捉えているかを少し説明した覚えがあります。それだけ共有できればあとは何の問題もありません。 光石さん、田口さん、森岡君、吉永さんがコーラスに参加した事はとても意義深かったと思います。最初に完成した曲を聴いた時は、コーラスの入っていないデモの方が良かったんじゃないかと正直思いました。でも何度か聴いているうちに、これで良かったんだと思うようになりました。光石さんと田口さんが「オーライ!」と歌っているんだから、そりゃオーライなんだろうと。

言いたい事は全て映画の中で言ったつもりです。一つ言えるのは、中高年世代の方々がもっと楽しく幸せになれれば、下の世代は歳をとる事を恐れずに、もっと希望を持って生きていけるはずです。そういう社会の方が健全だと個人的には思います。