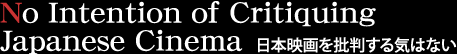映画製作において「発見」と「リスク」は大切な要素です。常に発見する心を持ちながら、映画を作りました。撮影の最中、なにか問題が起こり、迷いが生じても、私は決してくじけず、負の力を逆に新しい道を探す力に変えていきます。この方法で正解が手に入ると信じているのです。『CUT』の主人公・秀二のように、私は欲しいものが手に入るまで全力で戦います。それが監督の役割なのです。だからこそ、無謀とも思えるような挑戦をし続けるのです。
『CUT』は私自身です。始めから終わりまで、私そのものです。20年間、アメリカに暮らし、アメリカ人の感情やスピリットを理解し、アメリカを「第二の故郷」と呼ぶようになりました。私は自分の過去を宝物のように大事にしています。そして、映画作りにおいて私が学んできた価値観を忘れないようにしています。なぜなら、今、私たちが観ることができる素晴らしい映画たちは素晴らしき過去の映画があったからこそ作りだされたものだからです。これは『CUT』に込めたメッセージのひとつでもあります。
日本映画から非常に大きな影響を受けました。「駆ける少年」の動き、編集、音、特に映画の最後の12分間(台詞はなく、氷を持った子どもが火のそばを必死で走るシーン)は黒澤明監督の『七人の侍』のラストシーンに影響を受けています。「水、風、砂」は新藤兼人監督の『裸の島』、“Waiting”は小林正樹監督の『怪談』と市川崑監督の『ビルマの竪琴』の影響を受けています。複雑なカメラワークや長回しは溝口健二監督の影響を受けています。映画で子どもを扱うとき、街の色彩を決めるとき、大島渚監督の作品を参考にしています。清水宏監督は子どもの演技を撮る天才であり、我々の父でもあります。そして、小津安二郎監督の沈黙による表現を私は尊敬しているのです。
過去の偉大な映画作家たちは魂を映像に込め、芸術である映画を我々に残しました。しかし、彼らが遺した財産は風に去ってしまいました。インディペンデント映画は上映できず眠っています。このような映画を上映していた劇場はなくなりつつあります。
タイトルを『CUT』としたのは、現在の映画から汚れをカットしてほしいからです。
秀二が映画の中で叫んでいるように「映画は売春ではありません。映画は芸術です。我々は映画を尊敬するべきです」。もう行動を起こす時が来ています。今こそ動かなければ、「映画の真実」は燃えてしまい、灰しか残りません。そして次の世代には参考になるような映画はもう一本も残せないかもしれません。
TOKYO FILMeXで西島秀俊さんに出会ってから、秀二が生まれました。西島さんは私の作品をいくつか観てくれていました。私は日本映画を撮りたいと長年考えていたことを西島さんに話しました。
その後、何度も日本を訪れ、西島さんとお互いに興味を持っている映画や映画のアイデアについて話しました。『CUT』のシナリオを書き始めたとき、西島さんをベースに秀二のキャラクターを膨らませました。西島さんは秀二の台詞作りにとても協力してくれました。彼は才能ある役者であり、人間としてもとても素敵な人です。非常に困難な役柄だったにも関わらず、秀二役を全身で演じてくれました。
この映画の脚本は親友であるアボウ・ファルマンと英語で書き始めました。彼はカナダに住むイラン人でビデオアーティストであり詩人です。しかし、私はペルシャ語と日本語のニュアンスが近いことに気付き、脚本をペルシャ語に書き直しました。脚本は日本語に訳され、TOKYO FILMeXのプログラマーである市山尚三さんが青山真治監督を紹介してくださり、彼に脚本の監修をお願いしました。私は青山監督の『ユリイカ』を観ていました。素晴らしい作品です。青山監督とこの映画を通じて知り合えたことはとても喜ばしいいことでした。

昔からどこでも社会と芸術は衝突する時代があります。現在、マネーパワーはいつの時代よりも強くなり、芸術、特に映画を支配しようとしています。秀二の怒りはここから生まれています。秀二の宗教は映画であり、そのために必死で戦います。秀二が殴られ屋になるのは兄の借金を返すためですが、映画が置かれている今の悲惨な状況への反抗でもあります。そして、映画を単なるエンターテインメントにしてしまった人たちから、秀二はパンチを受けることになるのです。若い世代は「単なるエンターテインメント映画」を好みます。彼らの嗜好はビジネス街で決められているのです。この状況には変化が必要です。秀二の行動と本作は現在の映画業界に対する小さな抵抗です。秀二は『CUT』ですべてを叫びます。秀二は映画のラストサムライなのです。「映画の真実」を信じている秀二は自分の命をも投げ出せるのです。
映画製作現場では通訳の手を借りて、スタッフやキャストたちと繋がりました。英語を解っている人も多かったと思いますが、日本人はシャイなのか、英語で返事をしてくれませんでした。私は撮影のとき、現場や雰囲気が大切だと思います。互いの信用は約束や言葉では生まれません。監督が映像で何を言いたいのか、それをどう伝えるのか、それを実感して初めて信用が生まれるのです。このマジックがいつ起こるのか誰にも誰にもわかりません。『CUT』にもこのマジックが起きました。その後、あまり言葉を交わさなくても、お互いの言葉を理解できました。ひとつの目線、仕草、無言でもコミュニケーションがとれるようになったのです。
私は日本語を一切話せませんが、日本では言葉の壁を感じませんでした。台詞も私にはあまり重要ではありません。映画を観賞する際、台詞はきちんと聞いていますが、自分の映画ではあまり言葉を使いたくありません。私にとって、台詞は物語を進ませるひとつの要素ではありますが、台詞なしのイメージでストーリーを語りたいと思っています。映画作りへの情熱は映像、動き、編集そして沈黙で物語を説明することです。『CUT』において沈黙は主役そのものでした。
『CUT』を作るために何度も日本を訪れました。また、NYのMoMAやパリのシネマテークで数多くの日本のクラシック映画を鑑賞しました。作品を研究しながら何度も何度も観ました。名作を生み出した映画作家リストには多くの日本映画の監督たちの名前があります。私は日本映画を非常に尊敬しているのです。